ろうそくからロケットの燃焼まで

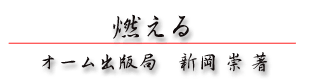
【青い炎と赤い炎】
ガスコンロの炎は青く、薪火の火は赤い。
ろうそくの炎やライターの炎は、よく見ると青い炎と赤い炎が混在している。
この問題について考えてみよう。
固体あるいは液体燃料の場合は、爆薬や固体ロケット推進薬のような特別な場合を除いて、酸素とあらかじめ混合することはしないから、燃える場合は拡散火炎である。
そのもっともポピュラーな炎であるろうそくについて考えてみよう。
図16に横断面を描いた。
ろうそくの「ろう」はいわゆるワックスで炭素(C)と水素(H)などがいくつも連なった高級エステル(酸とアルコールから水と分離して合成した化合物で、高分子のものとしては油脂などがこれに相当する)と呼ばれる一種で市販のものは通常融点(融け出す温度)で分類されている。これに芯(しん)をつけて円筒状にしたものである。

火炎があると、ろうに熱を受けて液化し、芯の周りに溜まる。芯は木綿糸で作られているので毛細現象で液状のろうを吸い上げる。吸い上げられたろうは、さらに加熱蒸発して火炎に向かって拡散していき、そこで空気中に拡散してきた酸素と反応して高温ガスを発生する。発生した熱は、再びろうそくを溶かす。これが一連のろうそくの炎のサイクルである。さて、炎をよく見ると、下部に若干青い炎が見え、大部分は赤い炎である。
火炎すなわち反応帯は基本的に青い。それは、いろいろな反応の中で生まれる化学活性種のうち、CHとかC2などが、おのおの青色や緑色などの発光を呈することによる。
各成分は、おのおの固有の波長の持った光を発するため、波長の分布(スペクトル)を調べることで、どのようなものが発生しているかを知ることが出来る。特にC2はスワン帯(Swanband)と呼ばれる緑色を呈し、予混合火炎でよく出るとされる。白鳥(SWAN)なのに緑色と呼ぶのは、スワンという人が発見者だったからである。
ろうそくの炎の基部にこのような傾向が見られるのは、火炎基部の開いているところから空気が若干入り込み、予混合火炎の性質を持つからとされている。
それからしばらく上方へ青い火炎が見られ、青い炎の上端の内側から赤燈色の部分が上方に大きく広がって、いわゆる流線型の全体像を作っている。
実は、炎が赤く見える部分は、広い意味で炎の一部には違いないが、燃料ガスと酸素の反応帯ではない。
燃料ガスは高温になると熱分解し、炭素(C)を解き放す。これを炭素の遊離と呼んでいる。
遊離された炭素は合体しながら上昇するが、高温であるため赤熱し、赤い炎に見えるだけである。炭素は反応帯で酸素と燃料もするが、燃えない炭素は合体を繰り返し、最終的に煤(すす)となって火炎から放出される。
したがって、厳密に火炎というのは、燃料ガスと酸素の反応帯とすると青色を呈するはずであり、赤い炎というのは存在しないことになる。
ろうそくの炎を暗いところなどでもう少し注意深く見ると、青い炎は赤燈色の部分の外側にかなり上方まで存在していることがわかる。赤く輝いているため、外側になるはずの青い反応帯が見えにくくなっているのである。この反応帯の発生する熱によって芯から蒸発してきた燃料ガスと空気が熱分解し、火炎が赤く見える。したがって、燃料ガスと空気があらかじめ混合されている場合は、酸素の存在によって炭素が合体して赤熱する。
時間的余裕がない場合、赤い炎とはならない。
ガスコンロの空気量を調整すればわかるが、内側の予混合火炎は、相当に空気不足(燃料過剰)の場合でも青色のままであるが、余剰の燃料が周りの空気と拡散火炎を作ると、やはり赤い炎となる。拡散火炎の場合は、特別な場合を除いてはほとんど赤い炎になると言ってよい。
一般に炭素を含む燃料ほど赤い炎になりやすく、メタン(CH4)、メチルアルコール(CH3OH)エチルアルコール(C2H5OH)も少ない。
アルコールの場合は、自身が酸素を含むことも原因している。
ろうそくの場合は「高級」エステルというくらい炭素を多く含むので赤い炎になりやすい。
炭素をいっさい含まない水素(H2)はもちろん赤い炎にはならない。
先ほど述べたような、青い色や緑色を出す原因もないので、まったく無色透明の火炎である。研究室で実験するとき、炎がついているのかついていないのかわからないときがあるくらいでわざわざ後で述べる方法で色をつけることがある。
一般に、都市ガスの場合外側の拡散火炎も青いのは、都市ガスが水素あるいはメタンが主成分であることによる。ところで、ろうそくの炎は赤い炎だから役に立つのであって、これが青い炎だったら輝きがなく、燈炎にならないので意味が無い。青い炎は手をそばに持っていっても暖かくないが、赤い炎は暖かい。赤い炎は、ふく射の量が多いので温かみを感じるのである。赤い炎のストーブはそばに寄ると暖かいが、青い炎のストーブはさっぱり暖かくなく、上方からの暖気の上昇が部屋を暖めるのを待つしかない。赤い炎のストーブがよさそうだが煤(すす)を発生する問題がある。
そこで青い炎を作ってその上を金網で覆い、金網を加熱して赤くする方法が最も良い方法と言える。
炎の色は青と赤だけでなく、いろいろな色が可能である。
たとえば、塩(NaCl)を炎の中に微量混入するだけで黄橙の火炎になるので、無色の水素火炎でも輝くことになる。これを「炎色反応」という。好みの色にできるといっても過言でも無い。種々の色を発するが、金属原子が高温のため活性化され、金属の種類に応じ特別な波長の光を放つことになる。上記に示すように、石英ガラス棒の先端に微少量付着させて火炎の中に挿入すればよい。
種々色反応については表に示すとおりである。
| 炎色反応の元素 | 元素記号 | 火炎の色 |
| カリウム | K | 紫 |
|
ガリウム |
Ga | 青 |
| 銅 | Cu | 青緑 |
| モリブデン | Mo | 黄緑 |
| ナトリウム | Na | 黄橙 |
| カルシウム | Ca | 橙 |
| ストロンチウム | Sr | 紅 |
| リチウム | Li | 赤 |

【炎の温度】
炎の温度は、どの程度になっているであろうか。
もちろん状況に応じてずいぶん変わるので一概にはいえないが、メタン、プロパン、そして市販のライターの燃料であるブタンなどは、同じ条件で燃やせば、その火炎の温度はそれほど変わらない。
それは、これら一般の炭化水素と呼ばれるものの重さ1グラム当たりに出す熱量(発熱量)は、燃料によってほとんど変わらないことによる。
たとえば適度の空気の量を熱量と混合させたときの混合比を理論混合比と前に比べたが、この混合比で理想的な状態で燃やしたときの火炎温度は、おおむね2,000℃
(2,200~2,300K)である。
この混合量からずれて燃料が少なくとも多くとも火炎の温度は低下する。

図18の傾向は燃焼速度を表した図9とまったく一致した傾向であることが気がつく。
すなわち、燃焼速度が大きいときは、当然火炎の温度も高い。
実は、前に述べた着火も、もとも着火しやすい混合比が理論混合比のときである。
しかし図18も注意深く見ると、燃焼速度のときと同様、理論混合比よりも若干燃料が過濃な混合比のところに火炎温度の最大値が存在している。
火炎温度2,000℃のように高温になると、安定な酸素分子(O2)も、二つの(O)に分解してしまう。
先に述べたように、これを熱解離と呼んで、ほとんどの分子に生じる。
この解離のためエネルギーを消費するので、火炎の温度は通常で1,000℃程度低くなる。
これを考慮すると、若干理論混合比より燃料過剰な混合比に最大温度は移動してしまう。
燃焼速度のときとまったく同様の理由による。実際に火炎を作ると、この火炎からいろいろな理由で熱が逃げる。これを熱損失と呼ぶ。たとえば円管の端を燃焼噴出口にして火炎を作ると、この噴射口が火炎から熱を吸収する。また前節で説明したように、赤い炎を作るとふく射熱を大量に放出する。このように実験方法によるいろいろな熱損失によって火炎の温度は低下し、なかなか真の火炎の温度が測りにくいのである。
ろうそく(パラフィンロウソク)の炎は1,400℃
アルコールランプの炎は1,700℃
水素やアセチレンは高く、おのおの、摂氏2,100℃及び2,500℃程度になる。
空気の代わりに酸素を用いるとメタンや水素の火炎は3,000℃近くに達する。
【無重力における火炎】
ろうそくの火炎は液滴と同様の変化が見られる。

著者の研究室で撮った写真と左側は通常の動場、右側は箱の中で燃えているろうそくを七メートル落下させ一、二秒経過したときのものである。時間が短く、自然対流が若干残っていると考えられるが、二つの違い見ると自然対流の影響が大きいことがよくわかる。
さらに時間を経過すると球状の青い火炎がろうそくの芯を取り囲むことを示されているが、最終的には消えてしまうという研究者もいて消えないとする研究者と議論が分かれている。
NASAがスペースシャトル実験でこの実験を行なったことがあり、数十秒後に消えてしまったが実験条件などいろいろ問題も多いし解釈も分かれており、当分議論が続くことだろう。
このほか、紙の燃え方、火花点火の挙動、前述した細胞状火炎の挙動などの多くが研究対象となっている。このように自然対流を除いた実験を必要とする場合のほか、噴霧や固体微粒子郡などの重力場における燃焼では、一個一個の微粒子が均一に分散しなかったり、着火前に沈降したりしていたため不可能だった実験に無重力を活用しようとする場合もある。
一般的に無重力は理想的な燃焼実験を行なおうとするために摘要される。
【家庭生活における火】
ろうそくの燃え方については、先に述べたので、ここでは重ねて説明はしない。代わりに停電でろうそくが見あたらないときの古式ゆかしい緊急対策を述べておくことにする。
日本では古くから用いられていた行灯(あんどん)の仕掛けのことである。図40に示すように、ろうそくとほとんど同じ理屈であって、油皿に、木綿の糸をある程度太く束ねた芯を浸して先端を出して火をつけたものである。
古くから用いられてきたが、燃焼学的にはずいぶんいろいろな問題を含んでいて興味深い。

油は古くから菜種油が用いられていたが、灯油でも構わない。しかし、これをガソリンやアルコールにすると、芯の先端だけに燃えとどまっておらず、油皿全体に広がって凄い危険である。ガソリンやアルコールは揮発しやすい、先に述べたように「引火」性が高いということになる。引火性が低いとなかなか燃料蒸気が蒸発せず火がつかないので、芯を出して芯の周りを炎で囲い蒸発しやすくするのである。
これによって芯周りだけが炎が存在し、その他へは燃え広がらなくする。前に述べたように炭素をたくさん出しやすい燃料は赤い炎となって煤が出やすいが光も出やすいので灯として優れている。光の量を倍増させたければ油皿の左右に二つの芯を設ければよい。しかしおもしろいのは、この二つの芯を近づけていくと、若干であるが二倍以上の明るさをだすことである。理屈を考えるためにろうそくを束ねた実験をしてみよう。

図41は直径6ミリメートルのろうそくを束ねて燃焼速度(ろうそくが減っていく毎分の長さ)を測った結果である。五本束ねると一本のときよりも約2倍の速さで減っていく。
芯の周りが炎で囲まれると芯への熱の伝わり方が大きくなっていくと述べたが、熱の伝わり方のうち、熱伝導(静止して物質の熱の伝わり)と対流による分は束ねてもそれほど変化しないが、ふく射は増す。
一本のときは、炎の外側へ出たふく射は周りを暖めるだけで、自分自身を暖めるには何の役にも立たない。二本以上束ねると互いのふく射熱を互いにある程度吸収することができるので蒸発量が増し、燃焼速度が増加する。しかし行灯の場合もそうであるが、二つの芯を近づけると芯が太くなっただけでの効果しかなく、明るさは倍増しない。
ろうそく五本ぐらい束ねると空気の内部への入り方が悪くなる影響もあってろうそくを束ねるほど明るくなるとは限らない。
束ねて明るくするためには適度の間隔が必要である。二つ以上の芯の火炎は互いの干渉がきわめて複雑なことがわかっていただけると思う。
釜でご飯を炊いていたころは、薪にいかに火をつけるか、どのように薪を組み合わせて燃やせばよいか、残り火でいかに仕上げるかなどのノウハウが各人各様にあったし、薪割りにいわゆるコツがあった。行灯は木枠に紙を貼って風よけした中に油皿を置くことになるが、ぼんやりした灯りが多少暗くなりかけると、行灯の中に手を入れて、燃えて低くなった芯を少しだけ油皿から引き出したものだと思われる。
このような直接的な火のコントロールは今ではほとんどなくなり、ボタン一つ押すだけですべてが最適に自動的にコントロールされるようになってしまった。良いようであるし、悪いようでもある。
ページ作成 2016.3.19


